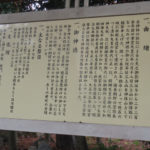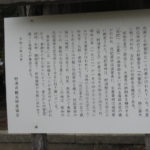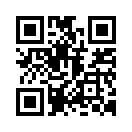今年も、大船さんの二階囃子にお邪魔してきました。


 太鼓方の親分とパチリ
太鼓方の親分とパチリ
みなさん、とても意気の合った演奏です。
曲の変わり目は、こうしてみんなに表示されます。
この日の、三回目のお囃子を後に、帰途に就きました。
ありがとうございました。
放下鉾さんも二階囃子を。
南観音山さんも。
北観音山さんも稽古しています。
10日の鉾建てからは、一気に祭りムードに入ります。
例年の節分は、壬生寺へは必ずお参りします。
そして、吉田神社か八坂神社へも廻ります。


今年の八坂神社の節分は、舞妓さん達の舞いの奉納が有るとの事でその時間に合わせてお参りしました。
そしたらまあ、何と凄い人出で舞殿には近寄ることも出来ず。
8人の舞妓さんの、髪だけを見せて貰って「祗園小唄」のお囃子を聴くだけ。
お参りして、お供物を頂いて早々に壬生寺さんへ移動です。



包絡「安全祈願」「健康祈願」「寛次.悦子」と書き込んで奉納してきました。
これが、壬生狂言の「包絡割り」で、豪快に割られます。
 そして、一年間神棚に飾る「達磨さん」も受けてきました。
そして、一年間神棚に飾る「達磨さん」も受けてきました。
 壬生さんの入り口の「元祗園さん」も、賑やかにお神楽を披露していました。
壬生さんの入り口の「元祗園さん」も、賑やかにお神楽を披露していました。

帰宅したら、歳の数だけ福豆を。とうとう、80個も食べる事になりました。
我が家では、初詣にお参りするのはその歳の「恵方」(縁起の良い方向)です。
今年は「東北東」が恵方とされているので、地図をみると「狸谷さん」が有りました。
家を出て、30分で狸谷さんの駐車場へ着き、250段の石段に取りかかります。



白龍大明神 七福神



弘法大師像 懐かしいこんな文字を見つけました。



この石段を登ると206段です。


 洛北が綺麗に見えます。
洛北が綺麗に見えます。
あと46段登ったらやっと本堂へ。
 初詣のお札を頂いてから、下山です。
初詣のお札を頂いてから、下山です。


 流石に「狸谷さん」
流石に「狸谷さん」
250段も、下りはラクチン。
 狸谷さんの「修行瀧」は、水が枯れたようで、長く使われてないみたいでした。
狸谷さんの「修行瀧」は、水が枯れたようで、長く使われてないみたいでした。
これでまた一年間、無事にすごさせて貰えますように。
八幡山では、毎年の「事始め」の日に行司さん(その年のお祭りを取り仕切る人)の
引き継ぎが行われます。



今年も12月13日に、令和5年の主行司さんから、令和6年の主行司さんへ
行司備品の一切が引き渡されました。
行司さん10数人は、主行司さんを中心にして、様々なお祭りの諸事万端を執り行います。
先ずは、12月30日の「注連縄交換」と、1月1日10時からの「新年拝賀式」の準備です。
みなさん、ご苦労様です。よろしくお願い致します。
毎年の8月16日は、萬木家の「お盆法要です」
 いつも月参りをお願いしている、教圓寺さんが来てくれます。
いつも月参りをお願いしている、教圓寺さんが来てくれます。



僕の姉と妹たち3人と、僕の子供達3人、それに孫は、7人のうち4人だけが集まりました。
読経を終えて、1時頃からは昼食宴会。
久し振りの出会いなので、話しが弾んで6時過ぎまで。
みんな元気で、また来年集まろう。

 僕は7時30分ころから地下鉄に乗って御所へ。
僕は7時30分ころから地下鉄に乗って御所へ。
丁度8時に御所に入ったら、大文字山に点火。
20分ほど送り火の灯りを観てから、また地下鉄へ。
こうして今年のお盆は終わりました。
祇園祭の前祭の鉾が組み始められました。
鉾が組み上がるまでは、町会所の二階でお囃子の稽古です。



長刀鉾の骨組み 放下鉾の二階囃子



函谷鉾町 霰天神山町 木乃婦さんの玄関


 太鼓方のリードで
太鼓方のリードで
今年も、大船鉾さんの二階囃子を訪問


笛方 鉦方
小雨の中、放下鉾の曳き初め。この日だけは、一般の人が曳く事が出来ます。
300メートル程曳いて、うちの前まで来てから、折り返してゆきます。


いよいよ鉾が建って、曳き初めを済ませたら「埒」らちで囲って宵山囃子です。

 皆さん、巫女さんの衣装で
皆さん、巫女さんの衣装で
菊水鉾さんは、大変力が入っています。


15日16日の夜は、烏丸通がホコテンに。人も店もいっぱいです。
人に流されて帰れなくなりそうなので、途中で引き返しました。
我が家は毎年元旦から、あちらこちらへ新年のお詣りに行きますが、いつも節分で全て完了です。
今年は一日早いお詣りで、まずは壬生寺から。

 節分前夜と言う事で、少し空いて居ました。
節分前夜と言う事で、少し空いて居ました。
コロナの為にお休みしていた「壬生狂言」も、再開されています。


 壬生さんの次は、吉田神社へ向かいました。
壬生さんの次は、吉田神社へ向かいました。
壬生さんからは、市バスで直行30分で吉田神社へ行けます。(敬老乗車証が嬉しい)
「節分と言えば吉田さん」壬生さんとは全然比べものにならないくらいの賑わいです。
屋台のお店も、壬生さんの何十倍も有ります。
 孫が通っている大学へ、ちょっと御挨拶に寄ってきました。
孫が通っている大学へ、ちょっと御挨拶に寄ってきました。
帰途もまた、有り難い敬老乗車証で市バスでした。
我が家から東へ徒歩五分の処に六角堂が有ります。
幼い頃からの遊び場でも有り、何かにつけてお参りしてきました。
正月の四日に、やっと六角さんへ初参りに出掛けました。


 お地蔵さんの前懸けも新調です。
お地蔵さんの前懸けも新調です。
綺麗に整備された境内には、多くの参拝客が見られます。
 活け花の池坊の本拠は、六角堂の傍の大きなビルです。
活け花の池坊の本拠は、六角堂の傍の大きなビルです。
六角堂のお向かいには「花市さん」と、花鋏の「金高さん」が控えて居ます。
お嬢様学校の池坊学園短期大学も、ここからすぐの処に有ります。
また一年、元気に過ごせますように御加護をお願いします。
今回の三上山初挑戦のあと、御上神社へもお参りしました。
それで初めて判ったのですが、三上山そのものが御上神社の御神体となっているそうです。
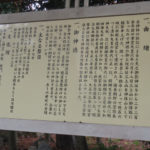


2200年の歴史を持ち、天照大神のお孫さんを祀るという、凄い由緒の有る神社です。



拝殿は重文 楼門も重文 本殿は国宝指定
 御神体の三上山は、御神山とも呼ばれます
御神体の三上山は、御神山とも呼ばれます
左が男山、右が女山
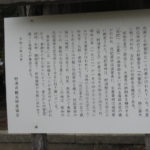

「大嘗祭」に献上する供納米は、ここから献上されるらしい。
「三上山に登られる方は、当神社の駐車場に車を停めて下さい」
なるほど、その意味が判りました。
二礼二拍手一礼。
雨の中、車折神社へお参りしてきました。
我が家では親爺の代から、いつもここへのお参りを欠かしません。


境内のツツジが満開で、良い時に行けたものです。
コロナまでは、車折神社の境内の「芸能神社」に掲げた俳優や歌手の祈願板を目当てに
沢山の修学旅行生が来ていましたがこの2年間、プッツリと途切れていました。
ところが、今日はその学生さん達が沢山来て、有名人の名前を見ては「キャーキャー」と喜んで居ました。
以前の賑やかさが戻ったのか、コロナと付き合うことになってしまったのか?
 壬生さんの入り口の「元祗園さん」も、賑やかにお神楽を披露していました。
壬生さんの入り口の「元祗園さん」も、賑やかにお神楽を披露していました。